『そっと背中を押してくれる(仮)』①③
- 2021.05.08
- 小説

梨沙子自身、自分の面倒くささに自分で面倒くさくなる時がある。
前の彼にプロポーズされた時もそうだった。
彼には”転勤することになったから、ついてきてほしい”と言われた。
好きだから一緒についてきてほしいのか、私だからついてきてほしいのか、それとも転勤についてきてくれる人なら私以外の誰でも良かったのか。
”ついてはいけない”という梨沙子の言葉に、彼は”わかった”と言ってそのまま私たちの関係は終わった。
そして今、また同じような面倒くさい自分が出てしまった。
「ねぇ、健二は子どもつくる気あるの?」
その言葉を聞いた健二の表情には少しの驚きと困惑が含まれていた。
「どうしたの?」と健二は聞く。
「いや、最近してなかったから・・・」
1年という私たちの限られた時間に焦っていたのか、それとも求められてなかったことを気にしているのか。多分、両方だと思う。
「そんなつもりはなかったんだけど、ごめん。タイミングもあるし、義務感のようになってもよくないと思ってたから。」
健二の言ってることはもっともだと思う。
「私の方こそ、急にごめん」
「こんな生活をしようって言いだしたのは僕の方だけど、今は今でちゃんと楽しみたいと思ってる。」
”どうしてわたしだったの”という梨沙子の気持ちが伝わったかのように、さらに健二はこう続けた。
「僕がこんなこと言える立場じゃないかもしれないけど、梨沙子のこと好きだよ」
梨沙子の曇りがかっていた心がその2文字の言葉によって、一気に晴れていくようだった。
いつもは別々の寝室で寝ていたが、
その夜は健二の寝室で梨沙子は眠りについた。
(続く)
-
前の記事

『そっと背中を押してくれる(仮)』①② 2021.05.02
-
次の記事
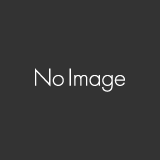
ブログの現状(2021.05.08) 2021.05.08